
「みそ」は、日本の風土が育んだ伝統的なプロバイオティクスです🍴✨
その歴史は古く、なんと1300年以上前には存在していたそうです!
今回は、日本人の食文化と健康を支えてきた「みそ」について紹介します📢✨
目次
歴史
「みそ」の由来
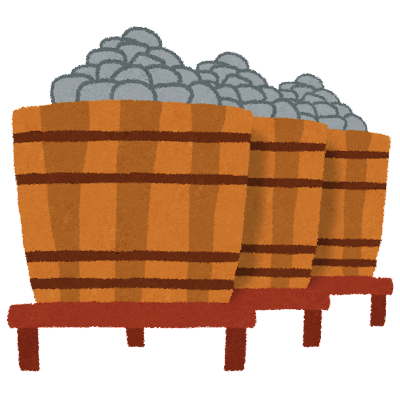
狩猟生活から農耕生活に移行した頃、作物を長期保存するため「発酵食品」が誕生しました。
中国伝来の「醤」が、「未醤(みしょう)」と呼ばれる大豆発酵食品として造られるようになり、大宝律令(701年)には「未醤」の記録があり、「未醤」→「未曽」→「味噌」と変化したようです。
その後、室町時代には1日3食になり、「みそ」が普及し、みそ汁が飲まれるようになりました。
戦国武将の戦いを支えた「兵糧食」

戦国時代には「みそがなくては戦ができぬ」と言われるほど、兵糧食として重要な戦略物資でした。
武田信玄は信州みそ、伊達政宗は仙台みそ、豊臣秀吉、徳川家康は豆みそ…と、強い武将がいる地=味噌処として、歴史と深く結びついていることがわかります。
その後も、日本各地の気候や風土に見合った形で独自に変化し、さまざまな「みそ」が誕生しました。
「みそ」は日本でしか造れない!?
日本人が1300年以上にもわたり伝統を守ってきた「みそ」。
実は、日本でしか造れないのをご存知ですか?
みそ造りに欠かせない「麹菌(アスペルギルス・オリゼ)」は、日本にしか生息しない菌なのです。
2006年に日本醸造学会によって、「国菌」にも認定されています。
日本は、雨がよく降り湿度が高いため、麹菌や発酵菌が育ちやすく発酵食品造りに適しています。
ほかの国で同じような材料を使っても、みそ造りはできないのです。
分類

麹
「みそ」の風味を決めるのが、カビ菌の一種である「麹菌」です。
米や麦、大豆を蒸し上げたものに麹菌をつけて繁殖させたものが、米麹・麦麹・豆麹です。
使用する麹によって米みそ、麦みそ、豆みそと、あわせみそに分類することができます。
味
甘みそ、甘口みそ、辛口みそと、「みそ」は味でも分けられます。
「みそ」の味は、辛さ加減を決める食塩の量と、麹歩合によって異なります。
塩の量が同じならば、熟成期間や製法にもよりますが、麹歩合が高い「みそ」の方が甘口です。
色
色によっても、白みそ、淡色みそ、赤みそと分類できます。
色に違いが出る一番の要因は、発酵と熟成にかける時間(醸造期間)の長さです。
一般に醸造期間が長くなるほど色が濃くなっていきます。
栄養
 「みそ」は “ 畑の肉 ” といわれる大豆を主原料にしています。
「みそ」は “ 畑の肉 ” といわれる大豆を主原料にしています。
大豆には水分やタンパク質をはじめ、脂質、糖質、ビタミン B1、ビタミン E、カリウム、マグネシウム、カルシウム、リン、葉酸、鉄、亜鉛、銅、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸、食物繊維など、じつに多彩な栄養素を含んでいます。
その一方で、コレステロールを全く含まないという特徴も持っています。
さらに注目すべきは、「みそ」の栄養価が原材料の大豆よりも、優れていることです。
「みそ」は、麹、酵母、乳酸菌などの微生物の働きで発酵しています。
それにより、大豆には微量であったアミノ酸やビタミン類を多量に生成します。
また、大豆たんぱく質が酵素で分解され、必須アミノ酸 8 種類も含まれています。
みそ汁1 杯の中には、想像もつかないほど多くの栄養素に満ちた世界が広がっているのです。
健康効果

「みそ」の健康効果は経験的なことから、様々なことがいわれてきました。
多くの大学や研究機関のテーマとなり、その研究結果が報告されているので紹介します。
●「みそ」など発酵性大豆食品は死亡リスクを低下させる
男女ともに発酵性大豆食品の摂取量が多いほど、死亡全体(総死亡)のリスクは低下。女性では「みそ」や納豆の摂取量が多いほど死亡リスクが低下していたが、男性ではその傾向はみられなかった。
これらは、日本特有の食品であり、 日本人の長寿の要因の一つと考えられている。
(詳しくは:大豆食品、発酵性大豆食品の摂取量と死亡リスクの関連 国立がん研究センター)
●みそ汁を飲めば飲むほど乳がんにかかりにくくなる
1990 年に行われた生活習慣に関するアンケートに回答した 40~ 50 歳の女性 2 万人を 10 年間追跡調査。「大豆、豆腐、油揚、納豆」では、明確な関連が見られないものの、「みそ汁」ではたくさん飲めば飲むほど乳がんになりにくい傾向があることが示唆された。
(詳しくは:大豆・イソフラボン摂取と乳がん発生率との関係について 国立がん研究センター)
●「みそ」は、高血圧の原因にならない
減塩のため、一日の塩分量は男性7.5g未満、女性6.5g未満が望ましいとされています。
お椀一杯のみそ汁には、約1.2gの塩分が含まれていますが、下記のような降圧効果も期待されています。
①大豆タンパク質の消化中間体ペプチドは、昇圧に関与するアンギオテンシンⅠ変換酵素(ACE)を強く阻害する。
そのため、味噌や醤油などの大豆発酵食品には、血圧上昇を抑制する効果が期待されている。
②みそ成分の大豆イソフラボンの降圧効果を示唆する報告例も多い。
③みそ汁は、野菜・いも・海藻などの効果的な摂取方法として評価されている。
④みそ汁は、カリウム や マグネシウム など降圧作用ミネラルの摂取方法として評価されている。
(詳しくは:味噌の科学と食塩 )
食物アレルギー

厚生労働省「保育所におけるアレルギーガイドライン 2019」によると、大豆は加熱処理ではアレルゲン性は低くならないが、発酵により低減化されるとの記載があります。
生成の発酵過程で分解が進むため、熟成期間の長い「みそ」ほど低減化度合が大きいようです。
また、味噌のタンパク質含有量は 9.7~12.5g/100gですが、調理に利用する量は少ないこともあり、重篤な大豆アレルギーでなければ「みそ」は利用出来ることが多いと記されています。
(アレルギー発症の閾値は個人差があるため、完全なリスクゼロとはいえません。)
しかし、近年増加している「大人の食物アレルギー」の中には、豆乳や発酵食品の納豆がアレルゲンとなる「交差アレルギー」も発見されています。
個人差がありますので、アレルギー専門医に相談しながら、ご自身の症状に合わせて食品をお選びください。
まとめ
「みそ」は、日本人の食文化と健康を支えてきた伝統的な調味料です。
栄養素が豊富に含まれるほか、天然の乳酸菌や酵母などの微生物が腸内環境を整え、日本古来のプロバイオティクスともいえます。
一日一杯のみそ汁習慣から、ぜひ始めてみませんか?☺🎵



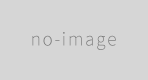



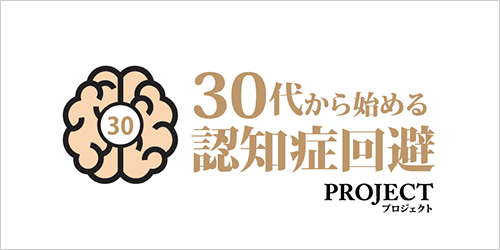



はっしー
管理栄養士